目次
はじめに
近年、日本およびアジアにおけるCBDの普及に伴い、CBDオイルやサプリメントを活用した健康法が注目を集めています。同時に、AI姿勢・筋バランス評価と組み合わせた施術も増加しており、セラピストの皆様にとって新たな可能性を秘めた分野となっています。
しかし、これらの分野には薬機法や医師法、あはき法など複雑な法的規制が存在し、知識不足による違法行為のリスクも高まっています。
本記事では、セラピストやトレーナの皆様が安心して業務を行うために、法的規制を踏まえた適切なアプローチについて解説します。
※重要な前提事項※
本記事は2025年1月時点での法規制情報に基づいて作成されており、法令の解釈や適用については必ず専門家にご相談ください。法令は随時改正される可能性があるため、最新情報は各関係機関の公式サイトでご確認ください。個別の法的判断については、薬機法に詳しい弁護士等の専門家にご相談することを強くお勧めします。
1. CBDの規制と普及の背景
厳格な禁止国
- シンガポール:CBDは規制薬物に指定され、海外でCBDを使用したことが判明した場合でも刑罰の対象
- 香港:2023年2月からCBD完全禁止。CBDが分解されてTHCに変換される可能性を理由に危険ドラッグに分類
段階的合法化国
- 韓国:2018年に医療用CBDの使用が合法化(アジアの中では他の国に先駆けて実施)
- 台湾:2019年にCBDの医療用途について使用が合法化
- タイ:2022年6月にアジアで最初に大麻を合法化。しかし2024年に政権交代で新たな保守連立政権が娯楽目的の大麻使用を禁止する方針を打ち出し、2025年1月から再規制が開始
日本のCBD普及が進んだ背景
日本は幸福度が低く、ストレスや不安、うつ病、長時間労働、引きこもり、不眠症など精神衛生に関する問題が山積みとなっており、代替的なウェルネス手段への関心が高まっていました。
2022年6月に発表された政府の骨太方針2022で「大麻に関する制度を見直し、大麻由来医薬品の利用等に向けた必要な環境整備を進める」と法的環境整備への期待が高まりました。
他のアジア諸国と比較した日本の特徴
- 段階的な法整備:厳格な禁止でも完全合法化でもない、成分規制による慎重なアプローチ
- 薬機法による規制:医療用でないCBDは、効能を具体的に明記することが出来ず、CBDを用いた施術についても同様の制約
- 企業主導の市場形成:政府主導ではなく民間企業による市場開拓が先行
- 品質重視の製品開発:法的制約がある中でも安全性・品質への要求が製品開発を促進し、市場は急激に拡大
本記事が、セラピストの皆様が日本のCBD市場の位置づけと今後の動向をより深く理解し、適切な事業戦略を立てる参考にして頂ければ幸いです。
2.CBDオイルやサプリメントの法的地位と最新規制
大麻取締法改正の重要なポイント
2024年12月12日から大麻取締法の一部改正が施行され、CBD製品に関する規制が大幅に変更されました。最も重要な変更点は、従来の「部位規制」から「成分規制」への移行です。
新しい規制基準「成分規制」
違法成分とされているTHC(テトラカンナビノール)の含有量による規制
- 油脂および粉末:THC含有量10ppm以下
- 水溶液:THC含有量1ppm以下
- その他:THC含有量0.1ppm以下
引用: 令和7年3月1日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
引用元: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
セラピストが注意すべき点
1. 製品選択の慎重さ:現市場に出回っているCBD製品の多くが基準をクリアできないのではないかといわれています。信頼できる検査証明書付きの製品の選択が不可欠です。
2. 薬機法との関係:CBD成分は、ストレス緩和や睡眠改善、肌荒れやニキビといった肌の疾患、または、肌質改善が期待されていると言われていますが、CBD製品については承認を受けていないために医薬品的な効能効果を標榜することは禁止されています。
3. 禁止される表現例:
- ❌「よく眠れる」「痛みが和らぐ」「血行が改善する」
- ❌「リラックス効果」「ストレス軽減」「筋緊張緩和」
- ❌「治療効果」「症状改善」「疾患予防」
4. 導入後の変化|“ただ測る”から“行動を変える”へ
3.科学的根拠に基づくCBDの理解
CBDの経皮吸収について
CBDは分子が小さいので、肌表面から塗布し、真皮層にまで浸透することで肌・筋肉などに働きかけることができます。局所的には経皮吸収による摂取が適しているケースもあります。吸収率は部位や方法によっても異なるため、慎重な使用が求められます。
重要な注意点
- 血中に取り込んで全身に作用させるには向きません
- 一般的なCBDオイルを皮膚に塗っても経皮伝達できるわけではありません
- 経皮専用製剤以外での効果は限定的です
安全性について
CBD単独で飲んでも飲みすぎると肝障害が起きることがあります。1日摂取量の上限は、英国食品基準庁(FSA)は食品からのCBD摂取を10 mg/日(5%CBDオイル約4~5滴)に制限するよう推奨しています。
引用:英国食品基準庁(FSA)、食品中のカンナビジオールの推奨される一日摂取量に関する勧告の変更を公表
引用元:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06150620160
4.ホリスティックなウェルネス体験の統合的アプローチ
近年、セラピスト業界では従来の手技によるボディワークと、CBDオイルなどの天然成分を組み合わせたホリスティックなアプローチが注目されています。
さらに、科学的な姿勢・筋バランス評価を組みわせる統合的な手法は、今後より広がる可能性を秘めています。
AI姿勢・筋バランス評価技術の適切な活用
1. 視覚的な姿勢バランスの確認
立位時の重心バランスの観察
肩の高さや骨盤の傾きなどの外見的特徴の確認
2. 筋緊張状態のAIによる評価と確認
表層筋・深部筋の緊張度合いの確認
可動域や柔軟性の確認
引用: ゆがみーるクラウドPRO
引用元: https://www.gsport.co.jp/yugamiru-cloud/
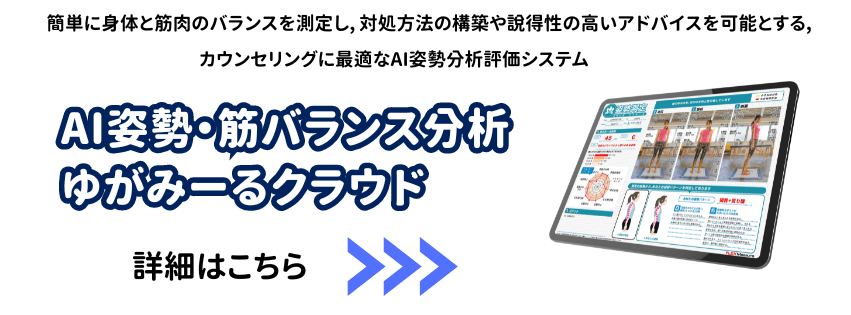
相乗効果のメカニズム(科学的観点)
物理的アプローチとの組み合わせ効果
AI姿勢・筋バランス評価と、CBDオイルと手技による物理的刺激により、以下のような相乗的な体験が期待できます。
1. リラクゼーション体験の深化
以下の組み合わせによる総合的アプローチにより、より深いリラクゼーション状態の実現、施術効果の実感向上が期待できます。
- 筋緊張の物理的緩和
- 血行促進による温感
- 触覚刺激によるリラックス反応
- CBDオイルによるリラクゼーション
2. セッション効果の持続性向上
- 即効性の要素
物理的アプローチや、手技による直接的な筋緊張緩和 - 持続性の要素
CBDオイル成分による持続的な影響、皮膚に残る香りと感触、心理的満足感の継続 - 結果としての向上
クライアントの満足度向上、リピート率の改善、口コミによる評価向上
5. 実践的コンプライアンス対策
日常的な注意点
- スタッフ教育の徹底:法規制に関する定期的な研修実施
- 広告表現の定期的な見直し:ウェブサイト、パンフレット等のチェック
- 製品の適切な管理:成分分析書や輸入証明書の保管
- 記録の保持:施術記録や製品使用履歴の適切な管理
専門家への相談体制
- 法的判断に迷った場合は薬機法に詳しい弁護士等への相談
- 自治体の担当部署への事前確認
- 業界団体等のガイドラインの活用
まとめ:安全で持続可能な事業運営のために
セラピスト業界における健全な発展のためには、以下の原則を遵守することが不可欠です:
1.法的制約の正確な理解:資格の有無による業務範囲の違いを明確に把握
2. 科学的根拠に基づいた情報提供:効果を過大に謳わない誠実な姿勢
3. 継続的な情報収集:変化する法規制への適応
4. 専門家との連携:不明な点は必ず専門家に相談
法令遵守は、セラピストとしての信頼性向上と事業の持続的な発展につながる重要な投資です。
※免責事項
本記事は2025年1月時点での法規制情報に基づいて作成されており、法令の解釈や適用については必ず専門家にご相談ください。法令は随時改正される可能性があるため、最新情報は各関係機関の公式サイトでご確認ください。個別の法的判断については、薬機法に詳しい弁護士等の専門家にご相談することを強くお勧めします。
参考情報
- 厚生労働省「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正について」
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」
- 矢野経済研究所「CBD製品市場に関する調査(2022年)」
お問い合わせはこちら

